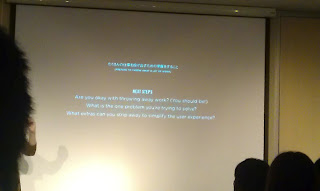2012/07/02に開催された『スタートアップデザイナーズナイト』のパネルディスカッション部分のノートです。質疑応答だけを抜粋しました。あと誰が何を話したかというところで確信がないので、回答者の名前は書いていません。
◆パネルディスカッション
Q.
コンセプトメイキングから入ることが多いと思う。そして、同時進行をいくつも走らせているかと思うが、気をつけることや抑えていかないといけないことは?
A.
・デザイン・サービスを作るときに、トップやチームがやりたいと思っていることがある
→どうもって生きたいのか、どういう世界を作りたいのか?
→どう具現化するかとか、それをどう落とすか?
・ただ単にデザインを作って終わりではない
→思いや世界観を具現化をしたい
・ヒアリングではすり合わせを行う
→ひとつの言葉の意味の確認をする
・言葉の意味をすり合わせることを大事にしている
→(相手が)ふわっとした言葉を使う場合、こちらから見せて「これは(あなたの言う)かわいいですか?」とか提示する
Q.
もともとデザインをはじめたきっかけは?
また、始めたころの勉強方法は?
A.
デザイン始めたきっかけ
・まず紙媒体から入った
→絵起こしのプロセスなどを学んだ
→DesignRulesという本を教えてもらった
→→テクニックベースで基本的なことが入った本
→→→色彩とか文字の大きさの及ぼす影響や、要素にまとまりを持たせるためには?など
→→→→これが基点になっている
A.
・デザインは人の目に触れるというところではじめた
・webをやりたい、表側の人間になりたいというところでデザイナになった
・デザイナのリンク集とか、関連している雑誌のレイアウトを真似して作るというのをひたすらやった
・真似に真似を重ねて今のスタイルになっている
・とりあえず見まくった
A.
・デザイナではないが、たくさん勉強をした
→本は買わなかった
→いいデザイナと仕事し、やり方・デザインの仕方をひたすら見た
→→「なんでこうしたのだろう?」「このバランス絶妙」というのを見て勉強した
・案件によってパートナーがいて、それぞれ得意・不得意や特性がある
→案件やデザインの方向を見て振り分けている
Q.
コミュニケーションで苦労している点は?
A.
・デザイナにテイストを話するとき
→経営者やクライアントの想定しているテイスト
→→それをデザイナにどこまできちんと伝えられるか?
・最初は苦労した。
→それは噛み砕いて伝えないといけない
→→ぜんぜん違うといわれて修正とかしていていた
→→→日々試行錯誤だった
A.
・気をつけていることはたった一つ「デザインとコーダの意思」
→ちょっとでもずれていると最終的なデザインがずれる
・コーダにはデータを渡すだけではなく意思を説明するようになる
→そうしないと全く別のものになったり、細かい部分が全部変わってきてしまう
・そういうものはチームで全てすり合わせる
→外部の人の場合はいつもより気をつけて伝える
A.
・運用段階でチームと何をするのかは、ぶれないようにしておく
→目的意識がずれてしまうとUIやテーブル設計、仕様に影響を与えてしまう
Q.
みなさんコンセプトメイキングから入っている感じだが、製作過程や完成までの流れはどうなっているのか?
A.
・コンセプトメイキングのテクニックはいっぱいある
→チームによって向いているものがある
・会議の場所を変えてものごとを考えるとか
→箱根にいって温泉につかりながらとか
→→そういう限定的な空間で時間をつめてンセプトメイキングを行う
・形にするところでは、先行するサービスやイケてるUIからペーパープロトタイピング
→そうやって人が使う動線を定義
→そうやって人が使う動線を定義
・それから、エンジニアが設計、デザイナがデザインを行う
A.
・コンセプト自体には全く意味がない
・ウェブサイトでコンセプトを伝えるのって非常に難しい
→車はかっこいいとかそういうもので買う。細かいスペックなどでは買わない
→でも、そのようなものをウェブで伝えるのは難しい
・何を伝えたいかをクライアントから聞く
→そこからどうみせたらいいかを決める
A.
・「こういう案件で、こういうクライアントで」と説明するとき気をつけていること
→自分がワクワクするかどうか
→→デザイナはどんなデザインでもできるが、想像性とかが出るように説明しないといけない
→→パートナーにも「このままじゃ面白くないとけど、こうすると…」とか
→→→そこまで作っていかずに、中途半端に人に渡してもいいものはできない。
・ワクワクできるものを提供できるように気をつけている
Q.
受託でやっているというが、リリース後も改善で入っている?
A.
・そういう形でやろうと思う
A.
・自分がやった分は最後まで
→ボタンの大きさとか細かいところまでやる
Q.
デザインってゴールがないけど、テストをどうしている?
A.
・自分の直感次第
→「悪いから何かを変えないと」というところでは自分の直感しかない
→クライアントと話あったりして変える
→→ダメならまた変える
A.
・"対ユーザ"と"対クライアント"で見ている位置が違う
→ちょこちょこアップデートを繰り返してユーザを飽きさせないのが重要
・ユーザを妄想するのは難しい
→でも効果検証すると強い
→仮説を立てデータを見て、その按配でどんどん改善を重ねる
Q.
改善のところとかどうですか?
A.
・スタートアップは公開したあとの方が重要
→ボタンの配置や色使いとかで数字がすごく変わる
・リリース後に数字を作るのがデザインの役割
→「データとしてこういう数字がでていて、ここが悪いからこうしたら?」とか
→ただ修正しようではない
・声や数字を参考にしてデザイナと作る
Q.
数字の取り方は?
大手はABテストを細かくやっていると思うが、スタートアップは?
A.
・google Analyticsとかは使う
→もっと本質的な見方は別にあると思う
→→勉強中
A.
・ボタンの検証は難しい
→みんな目立つように作ると思うが、目立たないことが原因ではない
→周りのレイアウトがボタンを隠している可能性もある
→→そこまでの流れが悪ければどれだけ目立ってもダメ
・数字を取るのは難しい
→twitterなどの反応を見るしかない
A.
・うちもgoogle Analytics
→細かいところ、テキストのネガポジ分析はできてない
・テキスト差し替えによるコンバージョン検証は毎日のようにやっている
→一時間ごととかで数字を出している
A.
・Closed Betaで意見が集まって面白かった
Q.
自分自身のやり方もそうだが、そもそもデザインの知識がなくてやっている人も多いと思う。
そういうときの課題は?
A.
・ウェブ未経験だけどこうしたい、こういう技術を使いたい、という人はけっこう多い
→それはそれでいいと思う
→分からないから私に声がかかる
・そのもやっとしたものを形にするのが私の仕事
A.
・スタートアップは好奇心旺盛でやりたいことが多すぎる
→多いのは良い
→それとユーザが欲するものの中間を捜す
・やってみたいというのは現実に戻すと可能性が小さくなるものが多い
→ユーザ目線でどうなるかをひたすらアドバイスする
→釘が出すぎる前にアドバイスするのが自分の仕事だと思っている
・やりたいことをなるべくそぎ落とさせる
→基盤ができてからやりたいことを追加させる
→100あったら50に落とし、75でストップさせる
・やるのは大変
→だけど、それを実現したり他の方法を提案するのが仕事
Q.
ユーザ系とプラン系で別れると思うが、その辺は?
A.
・ディレクターと話すときはバイアスがかからないように
→いかに自分達を客観的に見るかを注意するように
・改善案を盛り込むとき、方向があっているかどうかをよく確認
→声は聞いても、染まりきらないように
・バイアスがかかっていない状態で答えを見出すところに重点を置く
Q.
デザイナーとかコーダは自分で探すのか?
A.
・縁があって出会った人や紹介してもらった人と仕事をすることが多い
→昔からデザインをお願いするならこの人、という人が何人かいる
A.
・自分に合うかどうかもある
→それぞれ個性や得意なテイストがあると思う
→それをどれだけ引き伸ばせるか、というのは重要
Q.
日本と海外のスタートアップのデザインが似てきていると思うが、情報集めや真似するときのスタンスは?
A.
・どうしたらローカライズできるかという視点でサービスを見る
→基本的には文化が違うエリア
・海外の人は写真をものすごく上げるのが好き
→いい写真があればすぐ撮り、すぐ上げたい
・向こうでやりたいなら向こうの文化にあわせてスタートアップをすべき
→日本人的な感性相手にやるときは、日本人にあった切り口にしないといけない
A.
・アプリは似ていると思う
→webはまだまだ似つかない。
→似ていると思っているのは我々まで
・サービスを使うのが一般ユーザだと考えるとそこまでは踏み出せない
→海外のデザインを入れると違和感を感じるユーザが多い
・モバイルのUIならぜんぜん取り入れてもよい
→そこで浸透して最後にwebならよい
A.
・見たときに感じるものが日本と海外では違う
→海外ではcoolが好まれる
→女性向けだとかわいいを意識する必要がある
→→でもそれは海外には伝わらない。
・デザインを見せたとき、かわいいと思ってもらえるような感覚を大事に
→数字には出しにくいが…
・海外のデザインは好きだけど、日本では違うかなという気が
Q.
デザインセンスの磨き方。どういうサイトでインスピレーションをもらっているか?
A.
・ファッション雑誌を見ているのが多い
→海外のデザインや海外のweb award
・日本向けに作るときはファッション雑誌を参考に
→日本は青文字系とか赤文字系とか細分化しているのが独特
→それは紙面にも現れていて、受けるポイントが違う
・若い子はファッショントレンドをwebに感じる人も多いと思う
→最近のファッション雑誌を見て、トレンドを参考に
A.
・デザインセンスという言葉が好きじゃない
→自分がセンスがいいとも思わない
・何がいいと思うのかの定義づけも難しい
→みんな違う
・綺麗とされるウェブサイトには共通していることがある
→それは違和感がないということ
→→違和感を消していくとウェブサイトにピタっとはまる瞬間がある
・センスを磨くのは難しい
・横に対してそろっているとか、そういうものの組み合わせがサイトをまとめてくれる要因のひとつだと思う
・ウェブサイトを作るにあたって気をつけること
→余白をどれだけとってつくるか
→あとは写真のクオリティには注意
→フォントのサイズ。フォントサイズは比例するように
→→フォントがくずれると違和感しかない
→→三つのフォントサイズで作るようにしている
・いろんなウェブサイトを見て、水準を上げていく
→違和感を感じるスキルが優れていれば、綺麗といわれるウェブサイトにたどり着く
A.
・感覚を正すことだと思う
→センスという言葉は好きじゃない
・上のデザイナさんには引き出しを増やせといわれる
→それをいかに一般的な感性に当てはめるか?
・トレンドとか日常的に触れているものをストックすることが重要
Q.
サービスを作るにあたって、自分自身のデザイナとしての役割をどう考えているか?
A.
・受託という言葉のイメージ
→クライアントとデザイナが対等ではないと思われがち
→→みんな並列でやるという意気込みでやるべき
・デザイナやエンジニアの提案も面白いことが多い
→ぜんぜん違う見方の意見がでてきて、それが面白かったり、ブレイクポイントになったりする
・これからクリエイターの価値がどんどん上がっていくと思う
→彼らの価値を発揮できるようにしたい
→だから今のスタンスをとっているというのもある
・「なんかかっこいい」とか「いいな」というのを研ぎ澄まして仕事にいかしていくというのが面白い
A.
・デザイナとしての役割はクライアントの声を聞いて形をするということ
→ユーザに何も考えずに記憶させることが役割
・クライアントの要望や考えは最低限の要素
→それをいかにユーザに記憶させるかが勝負
A.
・二面性がある
→自分対ユーザ
→→デザイナとしてユーザにどれだけ楽しんでもらえるか
→対チーム
→→無言実行
→→"チームのモチベーションを高めるためにチームが喜んでくれそうなことを無言で実行することをデザイナーは求められる"というのがある
・世界への没入感を出すのがデザイナーの役割
→コンパスを組み立てるのが役割