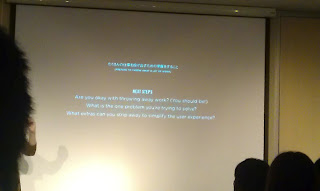2013年6月2日日曜日
【読書】【メモ】This is Service Design Thinking その1
This is Service Design Thinkingを読んだメモと50ページ目くらいまでのまとめ。
◇ざっくり読んだ感想
サービスデザインの定義には"学際的なもの"と書いてあって、たしかに多彩な観点からサービスデザインに関する記述がなされているのだけど… 「それ本当にサービスデザインに必要?」みたいなものも混ざりこんでいるような気がする。
例えば、この本には経営学の辺りの話題も幾つか出ていて(マーケティング、オペレーションズマネジメント、あと経営戦略)、たしかに読んでいて示唆はあるのけど、これらがサービスデザインのプロセスや考え方に対してどう関わり貢献するのか、という辺りの記述があまりない。
これは別にサービスデザインに経営学が関係ないとか言いたいわけではなくて、「同じ経営学でも、そこの領域ではなくない?」という。
『組織の文化や既に提供しているサービスを踏まえてサービスデザインをしなければいけない』 みたいな記述がこの本の中盤には繰り返しでてきて、これは明らかに経営学の観点から語れる領域なのだけど、そうであればマーケや経営戦略の人ではなくて、組織論について語れる人を連れてこないとしっくりこないというか…
--What is service design?--
◆サービスデザインの定義
・様々な学問領域から方法論やツールを集めた学際的なもの
・だから明確に言葉で定義できるものではない
◆五つの原則
サービスデザインの定義はないけど、求められる考え方を示すことはできる
・ユーザ中心 : 顧客の視点からサービスを見る
・共創 : デザインプロセスにステークホルダーも巻き込む
・流れがある : 相互に関係のあるもの同士の流れであるように見せる
・形に残る : 無形のサービスは物理的な何かで見えるようにする
・全体的 : サービスを取り巻く全ての環境を考慮に入れる
■ユーザ中心
・サービスは提供者と享受者のインタラクションで生み出されるもの
・享受者はそれぞれが違う経験や価値観を持っている
→それぞれを理解しようとすることからサービスデザインは始まる
・チームも同じ
→それぞれの知識を持ち寄ってサービスデザインするのが成功には必須
→→だからユーザ中心を共通のサービスの言語にする
■共創
・サービスのプロセスに関わる(様々な領域の)人を集めることが重要
・サービスをデザインする人は考えるのではなく場を作りアイデアを評価する
→ツールは適宜選ぶ
・共創は、顧客やサービスを実施する人達と行う
・ロイヤリティやエンゲージメントのためには、顧客を巻き込むことが重要
■流れがある
・サービスの持っているリズムは顧客に何かしら印象を与える
・顧客とサービスの接点
→人と人
→人と機械
→機械と機械
・サービスのステップ
→サービス提供前
→サービス中
→サービス提供後
・ワクワクするような印象を常に抱いてもらう
→ストレスを与えること無しに
・プロトタイプを作る
→サービス享受者がどう感じるのかを繰り返しテストする
■形に残る
・サービスは見えないところでひっそりと提供されていたりする(ハウスキープなど))
→形にすることで、サービスのことを印象付けてもらうことができる
→→ロイヤリティや推薦に繋がる可能性がある
・いつもそうすれば良いとは限らない
→サービスの流れやタッチポイントの中でやるのが良い
■全体的
・顧客は(意識していないかもしれないが)サービスを五感で感じる
・幅広いコンテキストからサービスのプロセスを見ること
・顧客の体験を素晴らしいものにしていくためには繰り返し改善することが必要
→現状の代替となるタッチポイントややり方を常に持っておくこと
・サービスジャーニーでステークホルダーが持つ印象を示しておくことが重要
→企業の文化、価値観、組織構造、プロセスがサービスデザインには重要
◆マーケティングとサービスデザイン
・同じ課題に対しての出発点やアプローチが違う
→マーケティングは共創のために顧客との関係を築く仕組み
→デザインはステークホルダーを中心に据えて、彼らと共創する仕組み
・サービスデザインの中心
→人・もの・組織の間にある価値
→それらの間にあるべき関係性
2012年9月28日金曜日
『Experience Vision のはじめかた』ノート
2012/09/26に開催された『Experience Vision のはじめかた』のノートです。
DevLoveは今日で93回目とのこと。あと7回で大台です!
◆山崎和彦様 - 自己紹介
◇経歴
・京都工芸繊維大学で工業デザインを専攻
・クリナップからIBMへ
・IBMでは工業デザインからソフトウェアのインタフェースデザインへ。ユーザエクスペリエンスデザインセンターを作った。
・その後はコンサルティングとして、UCDやUXを伝える活動
・そして千葉工業大学へ
IBM時代にアメリカ人の同僚が言っていた。「アメリカでは家に帰ってから勉強している。大学も単位辺り2万円でとれて、5年かけてMBAが取れたりする、向こうでは余暇としてそういう生き方ができる」
そういう生き方に興味を持って、神戸芸術工科大学・東京大学で手法を学び、現場で実践していった。いまも商品戦略ウェブ戦略パッケージングなどもやっている。
◇執筆活動
やり方をまとめることの大事さを思い、本も書いた。
・使いやすさのためのデザイン
・情報デザインの教科書
→この分野を学ぶための教科書として作った。
・プロダクトデザイン
→教えることが先生毎に違って、どうなの?と思って出した。工業デザインって、どこでも聞くけど、教科書がない。僕らが始めて作ったという自信ができた。
本として出版することで手法や考え方を使ってもらう。
自分が学んで経験したことを使ってもらえることで、社会に役に立ったと言う実感がある。
今日もその延長にある。
◆エクスペリエンスビジョンについて - どういったものか
◇エクスペリエンスビジョンについて
・ビジョン提案手法のフレームワークである
・新しいビジョン・サービスを構築するために役立つという視点から作った
・ユーザの本質的体験から見た、ユーザがもっと喜ぶような新たな体験を与えるため、本質的な価値と展望を探ることが目的
・本質的欲求からはじめ、上位の価値やサービスを考える
・エクスペリエンスビジョンのプロセスを全部使わなくても、全体像がつかめるようなテンプレートがある
◇エクスペリエンスビジョンの歴史
・エクスペリエンスビジョンは5年かけて作った
・ワークショップや合宿で実証していったら5年かかった
・いい手法はどんどん取り入れていきたかったから5年かかった
・世の中にあるものは使い、無いものは考え出した
◇エクスペリエンスビジョン本について
・エクスペリエンスビジョンで使用するテンプレートはダウンロード可能
・本を持っていなくても落とせる
・エビ本には、エクスペリエンスビジョンの適用事例・教育事例・ワークショップ事例も書いてある。
◇既存の手法をどんどん取り入れたことについて
・手法を考えた人は、それを使えば世の中を変えるような書き方をしてしまう。でもそれは嘘
・手法は一部分でしかない
・いろんな手法を上手く使いこなす。エクスペリエンス・ビジョンにはそういう役割を持たせている。
◆エクスペリエンスビジョンについて - 関連領域との関わり
◇ビジネスとエクスペリエンスビジョン
・エクスペリエンスビジョンにはビジネスの観点もある
・ユーザとビジネスの両方を見ている
・モノを売っている人がどうやってサービスに転換していくか?など
◇HCDとエクスペリエンスビジョン
・エクスペリエンスビジョンでは勿論HCDを使っている
・エクスペリエンスビジョンはユーザの価値に基づいて企画やエンジニアが提案するアプローチを取っている
・今までのHCDはユーザのニーズを受けるものだった
・今までのHCDは問題解決に寄っていた
・欧米のHCDの使い方やデザイン思考のアプローチを見ると、HCDはイノベーションの源泉としても使える
・HCDには問題解決と提案型の2つの使い方があり、それはプロジェクトに応じて使い分ければよい
◇シナリオとエクスペリエンスビジョン
・構造化シナリオを取り入れていることはエクスペリエンスビジョンの特徴
・シナリオができればユーザの本質的価値を評価できる
・シナリオを使えば、きちんとしたウェブサイトなどを作ることなく価値を調査することができる
・戦略的にやるときはバリューシナリオまでやるけど、日々のプロジェクトはインタラクションシナリオで留めたりとか …そういう使い方もできる
・ユーザ視点->プロトタイプ、ビジネス視点->ビジネスモデル、の形でシナリオの視覚化ができる
◆バリュー(本質的な価値)について
◇エクスペリエンスビジョンでは
・構造化シナリオ手法を使い、段階的に明らかにしていく。
・フレームワーク上では、上半分をユーザ・下半分をビジネス。それを真ん中のシナリオでつないでいる。
◇バリューなどの上位概念について取り組むということ
・これが曖昧だったりレベルが低かったりすると、いいアイデアが埋もれる
・そういうことはすごくある
・戦略作りはすごく大事
・プロダクトを作って、じゃあ2年~3後はどうするのか?ということが書いてない企画がほとんど。
・半年後の製品をただ考えるのと、ユーザの慣れも考慮したうえで2年~3年後のことを考えるのでは全然違う
・企画書は自分のウェブサイトや製品のことしか書いてない。戦略は戦略部門の話で別、となってしまう
・そういう中では新しいことをやるのは難しい
・新しいことには投資もリスクもある。それは単体の投資では回収できないことが多い
→だから、上のレベルで目標設定することが重要
◆ユーザについて
◇ユーザの本質的価値を知るためには
・提供価値分析やKA法という手法がある
・目の前の事象に対して、ユーザの価値や心の声を見つけ出していく
・潜在ニーズはフォトエッセイや行動観察で明らかにする
・顕在ニーズは日記や質問
◇ユーザ設定
・ビジネスを考えるのであればステークホルダーも必要
・ステークホルダー = ビジネスに影響を与える人
・優先順位をつけて、具体的な対象ユーザを明確にする
◆シナリオについて
◇シナリオとは?
・シナリオはモノとヒトの関係を表すことができる
・仕様書にはモノのことしか書いてない
・シナリオは日本語が読めれば分かる
・仕様書は専門家が見ないと分からない
・シナリオを介せばエンジニアとデザイナーが互いにコミュニケーションできる
◇構造化シナリオについて
・シナリオを階層化していることがポイント。
・バリューシナリオ(ユーザの価値 / なぜ?)
→バリューシナリオ:新規性・魅力がポイント
→ユーザ・ビジネスにとっての価値
→ユーザにとっての本質的欲求がビジネス提供者の提供方針がベースになる
・アクティビティシナリオ(ユーザの行動 / 何を?)
→バリューシナリオの1シーン
→ユーザの活動の全体が分かるように描く
→ペルソナはこの段階ではっきりしている必要がある
→有用性・便利さがポイント
・インタラクションシナリオ(ユーザの操作 / どうやって?)
→効率・全体としての使いやすさがポイント
→アクティビティシナリオの1タスク
→具体的なモノ、その使い方を書いていく。
アクティビティシナリオとインタラクションシナリオの違いについて。アクティビティは人の行動なのでモノははっきりしていない。逆に、インタラクションはモノがはっきりしている。例えば、朝気持ちよく起きるのはアクティビティで、それを照明器具でやるというのがインタラクション。
◇シナリオの評価方法
・ユーザの側面からの評価方法(代表的なもの)
→魅力性・新規性・有効性・効率性。
→魅力と新規は満足度に関係する
→有効と効率は便利さに関係する
→どれを評価するのかはプロジェクトの段階で変わる。例えばバリューの段階なら効率性より魅力性や新規性を見る。
・ビジネスの側面からの評価方法
→戦略性・事業性・市場性・実現可能性・社会性
→例えば、最初のバリューの段階で戦略を評価し、アクティビティで市場性を見て、操作で実現可能性を見る
→3年後の話を考える時に操作性の話をするのは違う
◆エクスペリエンスビジョン・情報デザインに関して出てきた話
◇問題解決と提案
・問題解決のプロジェクトは必要だけど、それだけじゃダメ
・新しいものやこれまでなかったものを考えるためにはユーザの本質に立ち返って、エンジニアからユーザに提案することが必要
・ただ提案するだけではなくて、ユーザの立場から提案することが重要
・ユーザの価値に基づいてビジョンを考えると新しいものが見える
◇企画提案書について
・技術・実現可能性がポイント
・総合的なビジネス企画を立案する
・製品やサービスに対するユーザ要求仕様をまとめる
・ユーザ視点から見た仕様の根拠を書く
・うれしい体験 - 「HCDから見たポイント」「差別化・新規性・魅力」を書く
◇本質的な価値の見つけ方
・本質的な価値を見つけるのは難しい
・バリューシナリオを作って共感度を見ていくのがよい方法だと思っている
・シナリオ作りならお金がかからないので、そこを評価して価値を見つけていけばいい
・何もないところからブレストしても仕方がない
・砂金取りと同じで数を打たないと駄目。
・新しいものはどこにあるかわからないので、広くユーザにアプローチすることが大事
・そのためにはできるだけ簡単な形で聞く方がよい
・シナリオは完全なプロトタイプよりも量が作れる
・シナリオなら「こんなものも?」という、プロトタイプでは(費用と優先順位的の兼ね合いで)試せないようなものについても調査ができる
◆もう少し周辺の話
◇ゲームチェンジについて
・同じ土俵で戦うと安くて効率のよいところには勝てないというのがある
・そういうとき、欧米ではゲームチェンジを使う
・アメリカは自分達でルールをどんどん作っている
・改良だけで日本がやっていくのは今後難しいのではないか
・目の前の問題を解決するのではなくて、ユーザに本当に必要なものを長い目で見て戦略を立てることが大切なのではないか
「新しい目覚まし時計をデザインして?」と言われると、既知の固定された記憶の中でデザインしてしまう。そうではなく「朝、気持ちよく起きることができる体験をデザインして?」とすると、1つ上のレベルで考えることができ、もっと自由な提案ができる。チェンジゲームというのはそういうこと。
◇スケッチとプロトタイプの違い
・散策的にアイデアを作るのがスケッチ
・検証的なものがプロトタイプ
◇新しいサービスの確かめ方
・イベントを1回だけやる。ユーザにとってうれしいかどうかはそれだけで判断できる
◇アクティングアウトの使い方
・いろいろある。実際に設計者が使ってみるとか。
◇クイック&ダーティ
・クイック&ダーティに実験することがすごく大事
◇構造化シナリオはウォーターフォールっぽくない
・アジャイルとシナリオは近い
・どこまで深くやるか?という違いだけの話。
・アジャイルはソフトウェアまで作るが、(エクスペリエンスビジョンでは)クイックにシナリオ・プロトタイプを作って済ませる
・クイックに作るのが大事
◇心配していること
googleが自動運転の車を街で走らせ、実証的に走り方をプロトタイピングしている。日本は法律上そういうことが絶対にできないと言われている。iRobotもろうそくが倒れたら火事になるからできなかった。そういう日本人の潔癖さが、機会を遠ざけていることを心配している。
◇異文化
アメリカでは、新しい発想をするためには異文化の人がいないという認識をする人が多い。技術者・マーケティングの人・デザイナー …そういう人が混ざることで新しいものができるという発想が大事だと思う。
山崎和彦様, DevLove様, ありがとうございました。
2012年5月6日日曜日
『第9回情報デザインフォーラム - 情報デザインのワークショップ』ノート
2012/05/04に開催された第9回情報デザインフォーラムのノートです。素晴らしい講演がたくさんあった。だからその講演内容を的確にまとめてみよう…! と考えていたのですが、見返すとノートの半分は私の感想でした。
なお、当フォーラムのテーマは『情報デザインのワークショップ』であり、8人の講演者による発表と学生によるパネルディスカッションがありました。パネルディスカッションはただただ見いってしまったので、ノートはありません。
なお、当フォーラムのテーマは『情報デザインのワークショップ』であり、8人の講演者による発表と学生によるパネルディスカッションがありました。パネルディスカッションはただただ見いってしまったので、ノートはありません。
◆オープニング
情報デザインのワークショップという本を作るために資料を持ち寄って集まったら、その資料の内容がよくて、だったら発表しようじゃないか …という流れで今日があります。という話でした。ハイスキルな人同士が集まっているからこそ成り立つ、この頂上決戦的な流れは好きです。
◆第一部 大学でのワークショップ
◇山崎和彦氏 - 『情報デザインのワークショップ・プロジェクトと体験ワークショップ事例』
体験という言葉とワークショップとの関係性についての話がメインでした。たしかに、参加者が体験をとおして『学び』を得るという、ワークショップが持っている特性を語るのであれば、『体験』が持つ意味や価値について論じるのは重要なことだと思いました。特に印象に残ったのは「ワークショップを誰とするか?」という話です。割とあっさりと触れただけだったのですが、このくだりを聞いて、私が持っているワークショップという概念についての認識は飛躍的に広がりました。 …というよりは、自分の体験によって植えつけられたワークショップという概念についての認識が矯正されたというか。人と人のコミュニケーションを通して作り上げていくものがワークショップである、というあたりまえの点について自分の中で勝手に枷を作っていたのだな、と反省することしきりでした。
以下、メモ。
・ワークショップは知識を得る場所ではなく、作り上げて本当の学びの楽しさに目覚めるためのもの。
・ワークショップは知識を得る場所ではなく、作り上げて本当の学びの楽しさに目覚めるためのもの。
・ワークショップでは『体験』することが重要。つまり、ワークショップ自体のデザインが重要になる。
・ワークショップにおける体験の分類
・ワークショップを誰とするか
- 自分が体験
- チームと一緒に体験
- ユーザの体験をする … デザインのワークショップでは重要
・ワークショップを誰とするか
- デザイナ同士
- デザイナ・ユーザ間
・体験とワークショップの関係
- 体験を観察するワークショップ … 相手を理解する
- 体験から発想するワークショップ … アイデアを広げる
- 体験を視覚化するワークショップ … 個人的な作業を共有・評価し広げる
- 体験とビジネスを考えるワークショップ
- 体験と社会環境を考えるワークショップ
・ワークショップの目的
- 学ぶ楽しさ・自主的な学び
- 発想の拡大・視点の広さ
- 共有・合意形成
- 相手の理解促進
◇原田 泰氏 - 『インフォグラフィックスを通して学ぶコンテンツ・デザイン』
図や絵は言葉と同じであるという価値観を持っているということをおっしゃており、実際にスライドの中で使われているインフォグラフィックスを見ると、ポテンシャルが高い表現技法なんだな、と興味を惹かれました。
- インフォグラフィックスの制作工程
1-1. 現実
1-2. 解体
1-3. 再構成
1-4. 表現
1-5. 魅せる/反応
↓
(フィードバック)
↓
2-1. 現実
2-2. 解体
…
- この説明の際に使用している図が印象的でした。現実をパズルのピースのように解体しそれを再構成している図なのですが、メッセージがとても明確に伝わってきて、それが非常に印象に残りました。後で参考にしようと急いで描き写したのですが、私の描いた絵はまるで小学生の落書きみたいな感じになっていて、当初の意図とは異なる”味”のようなものを醸し出していました。スライドの写真を撮っておけばよかったとつくづく思います。
- コンテンツ・デザインはメッセージを自分の言葉で表現し人に伝えるものである。
- インフォグラフィックスの利点は『人に伝えることができる』『次の工程で再利用できる』ということ。
- このような教育を行なう意図 ・ラピッドプロトタイピングをする体質を作りたい
・自らフレームワークを作り、使いこなせるようになって欲しい
インフォグラフィックスの視覚言語としての表現力と可能性を目の当たりして、モホリ・ナギのフォトモンタージュ作品やその造形理論をおさらいし直したいなー、とか思いました。
◇上平崇仁氏 - 『デザインワークショップの故きを温ねて新しきを知る試み』→『昔の事例を再解釈して新しいデザインワークショップをやってみた』
過去の人達が作ったり実践したデザイン性の高い作品・授業・ワークショップを元にして、ワークショップを作成しているという話をしていました。そして、ワークショップを作り実践する中で浮き上がってくるものを指して「過去の事例から変わらない大事さが見える」ということを言っていました。時代を越えて普遍な大事なものがあるよね? ということです。また、過去のワークショップに学ぶことについて「そうしないと先人の実践が埋もれたままになってしまう」といった趣旨の話をしていたことも印象的でした。
そのほかにも、ワークショップやその周辺の概念についての見解を述べていたのですが、この点についても関心することしきりでした。一方的に教えるというやり方のデメリットの話から、これを裏返す形でワークショップを選択することの理由を導き出したりしており、私は見事に説得されました。
以下、メモ。
- 何故ワークショップか? 『人は言えば聞き、聞けば理解する』わけではないから。
- 学びは、知識をためるものではなく、社会的に構成されるべきもの。
- 教えることにはデメリットがある。教わる側に固定観念ができ、それによって思考停止してしまう。だから、教えるより自分で学ぶ(ワークショップの)方がよい。
- ワークショップのツールに重要なこと。道具になっていて、参加者がお互い確認ができるというオープン性があること
- ワークショップには限界がある。参加することでやった気になるが、自信には繋がらない。また、ワークショップ中毒者というものが存在しており、彼らは週末温泉に行くかのごとくワークショップを利用している。
・ワークショップの構成要素
- 身体
- 協働
- 創造
- 共有
- プロセス重視
・ワークショップのポイント
- 先生はいない
- 客ではいられない
- はじめから答えがあるわけでない
- 頭とからだが動く
- 交流と笑いがある
・ワークショップの切り口
明確に切り分けできないが、次の2つがある。
- ワークショップを通して何かをデザインする
- デザイン手法や考え方をワークショップで学ぶ
・まとめ
- デザインにおいてワークショップと実践は同等
- 過去の事例から変わらない大事さが見える
◇安藤昌也氏 - 『写真を使った価値マップによるサービスアイディア発想』
サービスデザインの領域がだんだんと拡大しているという話と、ワークショップに適用する概念として『AT-ONE』というものがあるという話をしていました。で、後者の『AT-ONE』についてUXをする人が陥りがちな点と、重視すべき概念について話をしており、なるほどなーと思いました。
以下、メモ。
・サービスデザイン領域の拡大
- 『ニーズの充足』自体を価値とし、それを提供
- 『欲求の実現』体験した人が感じることを価値とし、それを提供
- 『意識→参画→価値』価値ではなく機会を提供
・AT-ONE
- Actor 登場人物を広く
- TouchPoints どうつなぐか
- Offering 何を提供しているか
- Needs 本来満たすべきニーズは何か
- Experience
・AT-ONEのポイント
- Offeringが重要。
- Offeringを正しく導けば、正しいActorやTouchPointsを導くことができる。
- UXはNeeds, Experienceを考えがち。
◆第二部 社会人のためのワークショップ
◇木村博之氏 - 『インフォグラフィックスは自分で考え行動させるためのキッカケデザイン』
インフォグラフィックスやコミュニケーションの手段に留まらずプロダクトへ適用範囲を広げているという話が大きかったです。デザインが求められる領域がどんどん広がっているというか、デザインに対するリテラシが大きくなっているのだな、という話です。個人的には、デザインに予算を投下できないようなプロジェクトでも、それなりのデザインを持っていることは大前提になるのではないか? という気がしています。私はそちらの方がいいので、情報デザインやユーザエクスペリエンスという技術が、世界にあまねく浸透し広がってくれることを本当に期待しています。また、ワークショップに参加することについて述べた際に「自分で考え行動するためのきっかけでしかない」と言い切っていたのが非常によかったです。
以下、メモ。
・フレーミング・リフレーミングが重要
・インフォグラフィックスの作成手順
(だいたいこんな感じだったような…)
- 伝えたいことを決める
- データを集める
- 伝えたいことを再考する
- 表現を考える
- 情報を絞り込む
- レイアウトを考える
◇小路晃嗣氏 - 『組織におけるワークショップの目的とその運営のためのポイント』
組織とワークショップという、私にとってピンポイントかつ即効性があるという非常に気になる講演でした。内容も期待を上回る素晴らしい内容だったのですが、全体としてメモがぜんぜん追いついていかなったという… 非常に残念です。「もっと大事な情報がたくさんあったような気がするのだけど…」と、ノートを見返す度に思います。スライドが公開されることを祈るばかりです。また、『ワークショップ開催のポイント』の箇所のスライドで、皆がカメラを取り出して撮影しまくっていたのは非常に印象的でした。私も確固たる決意を持って撮影に望めばよかったと思います。
・ワークショップの開催は継続して行なうことが大事、というのが結論。
・ワークショップには縦割りの組織の中で機会がないような人々が会う、というメリットがある。
・会社では費用対効果が求められる
・ワークショップ開催のポイント
- 儲けること前面に
- 責任と範囲を明確に
- 継続できるように
- 収支バランスを図る
- 税で社会に貢献する
・ワークショップ開催の合理的な側面
- マニュアル化して誰でもわかる(開催できる)ように
- レビューと改善を行なう
・ワークショップ開催の俗人的な側面
- メソッドやガイダンスとして余白に表現する
- 人間力によるOJTを行なう
◇脇阪善則氏 - 『UX TOKYOとワークショップ - サード・プレイスとしての機能と役割』
『ユーザエクスペリエンスのためのストーリーテリング』の翻訳者です。非常にためになる本で、たびたびお世話になっております。今回は『UX TOKYO』を基点として、ワークショップの機能と役割について述べていました。特に印象に残ったのは、ワークショップを開催・洗練させていく中から非常に具体的な成果物を作り出す、という展望に関する話です。私にも計画的にものを見る視野が欲しいと思いました。
以下、メモ。
・ワークショップとは
- 本の学びを実践する場
- 実践の場
- インプットした知見を消化してアウトプットする場
- 新しいことに挑戦する場
・ワークショップを通して経験の蓄積ができる
- 実施
- デザイン発想
- フレームワーク化
- 技術仕様化
◇浅野 智氏 - 『企業にHCDを根付かせるワークショップとその開発』
『何かを教える』ということと『教えるということについて責任を持つ』という点について、非常に印象を受けました。私の持っている価値観に「『何をすればいいか?』よりも『何故そうしようと考えるのか?』という、その人の持っている行動原理や価値観に触れたり想像できることが非常に重要である」 …こんなものがあるのですが、この講演はこの点について強く働きかけるものでした(あくまで私の印象です)。また、講演内容には実用的な内容も多々含まれており、学びがたくさんありました。
なお、特に強く印象に残ったのは、HCDを教えるためには7回のワークショップが必要ということと、この点については絶対に譲れないというものでした。つまり、「3回でやってくれませんか?」というお誘いがあっても、HCDを教えるためには7回のワークショップが必要なため、断固として無理、という話です。『断る』『譲らない』という行動や価値観について、私にはここまでの力強さがありません。だから印象に残りました。
また、ワークショップの構成についての考え方も参考になりました。
- 概論について講義し、以降の学びのメンタルモデルを形成する(これは絶対必要)。
- 全体像がわかるワークショップを行なう。
- 以降は個別のテーマについてワークショップ。結果がでやすいものから行なう。
その他、メモしたポイント
- ワークショップは楽しいことが大事。
- ワークショップを作る時はただ思いついたものではなく、もっと長いスパンで教えているようなものを落とし込む。
- ワークショップでの学びが根付くところとそうでないところがある。社内に強力な推進者がいるところなら根付くが、トップダウンでやっても定着しない。
後援者の皆様, パネルディスカッション発表者の皆様, 主催者の皆様, ありがとうございました。
『第9回情報デザインフォーラム - 情報デザインのワークショップ』感想
2012/05/04に開催された第9回情報デザインフォーラムの感想です。情報デザインのワークショップというテーマについて、8人の講演者による発表と学生によるパネルディスカッションがありました。以下はフォーラムに参加した感想です。
あと、『情報デザインの教室』は買っておこうと思いました。
◇情報デザイン及びUXの価値が高くなっている
山崎氏が体験とビジネスを結びつけることについて述べていらっしゃいました。木村氏はインフォグラフィックスがコミュニケーションの手段にとどまらず、プロダクトの領域に進出しているという話をなさっていました。浅野氏は「PCをすっとばしてスマホを手にするユーザが増えており、彼らは利用するコンテキストに合わないプロダクトをわざわざ使おうとしない」という話をなさっていました。
また、元IDEOのElle Lunaさんが来日した際におっしゃっていた話の中に「市場の評価におけるデザインの割合が大きくなっている」というのがありました。「そんなところにまでデザインの概念とその重要性が広まっているのか」という印象とともに深く印象に残ったのですが、前述したようにこのフォーラムの中でもデザインの価値が繰り返し取り上げられており、デザインという概念がビジネスのさまざまな領域に織り込まれ始めているのだということを改めて認識しました。
◇人間中心設計とワークショップは親和性が高い
ざっくりとした言い方になりますが、協働するという点において、これらは非常に似ていますよね? 互いの(前向きな)コミュニケーションをとおして成果物を制作するというプロセスは同じなわけです。それから、(けっこう大事なことなのですが)成果物を評価する基準も何か似ているような気がします。
私がメインとしている業務系のソフトウェア開発の場合、利用者とプロダクトの所有者と開発者の利害は著しく一致しないという問題があり、求められるコミュニケーションのベクトルがワークショップのそれとは違うのです。予算と納期と品質と機能があって、それぞれについて三者間での落としどころをひたすら探すというか …そういう観点から見ると、情報デザインとワークショップの親和性の高さは羨ましいです。
◇ワークショップの開催目的をはっきりとさせることが重要
ワークショップをとおして考え方を学ぶ、という話であればワークショップはそれ自体が目的となります。他方、ワークショップをとおして何か有意義な成果物が作りたい、という話であればワークショップはあくまで手段ということになります。前者であればワークショップの参加者に求められるのは参画する意識と必要最低限の予備知識ですが、後者であれば参画する意識よりはきちんとしたアウトプットを出せるだけのスキルが重要になるでしょう。ワークショップを開催するにあたって、これらの区別を行わないということはあまりないでしょうが、もししなければ散漫になってしまうのかな? と思いました。
◇主催者・参加者それぞれがワークショップについての学びを持ち帰ることが重要
ここでいう学びは『ワークショップについての学び』です。
ワークショップ自体はそこそこの歴史があるものであり、学びの手法として強く根付いているものだと思います。そういう意味では、ワークショップというものはなかなかに語りつくされており、それが何であるかという議論も一通り出尽くしているのかな、とも思います。
一方で、このフォーラムの講演でもワークショップにおける体験や経験が未分化のまま語られることがあったりして、まだまだ発展途上で未知の領域が沢山あり、だからこそワークショップについて学ぶことが重要なのかな、と思いました。
ワークショップに参加したけど「あまり発言できなかったし、得るものが余りなかったな~」という経験や、ワークショップを主催したけど「みんなピンと来ない顔をしていたし、ディスカッションも盛り上がってなかったな~」という経験など、こういったものをうまく整理してくれるような概念やプラクティスが揃ってきてくれるといいと思います。
◇ワークショップはあくまで学習の一手段であり、銀の弾丸ではない
ワークショップが何であるかという話や、ワークショップの持つ特性、ワークショップの持つポテンシャルなど、いろいろな観点からワークショップについて語られていました。そういったメリットについての話の総体として、ワークショップは座学を超える学習の手段なのだな、という感覚を抱きました。他方、ワークショップが持つ中毒性を温泉に例えて警告を発している方もいました。また、ワークショップを通して学んでも、それが定着しない組織がある、という発言もありました。で、良いところと悪いところをまとめると、ワークショップが有益であることは間違いないが、それは適切な使い方があってこそなのだと思いました(当たり前のことですよね)。
また、ワークショップは協働という形態を取るので学びを共有することは必須です。なので個々人が学びを深堀りする必要があるテーマの場合や、学びに個人差が生じやすいようなテーマの場合、ワークショップは逆に弱いのかな? とも思いました。
後援者の皆様, パネルディスカッション発表者の皆様, 主催者の皆様, ありがとうございました。
2012年4月7日土曜日
『 IDEOディレクターElle Luna氏とOneSheetの創業者Brenden Mulligan氏による「Startup Strategy」』ノート
2012/04/04に開催された『 IDEOディレクターElle Luna氏とOneSheetの創業者Brenden Mulligan氏による「Startup Strategy」』のノート。
これはElle Lunaさんのプレゼンテーション。
※管理人のヒアリングスキル及びあくまで意訳であることには留意してください。
 |
◆Elle Luna 『How you can think like a designer To make difference in your startup』
- 『デザイナーのように考え、スタートアップを差別化する方法』
◇はじめに
今日お話するのは、本当に具体的なことです。
IDEOを辞めスタートアップの会社に入ったときくらいから、ずっと考え続けてきたことです。
スタートアップにあたり、デザイナーのように考えるには? ということについて話します。テンションがあがってしまいます。
◇何故デザイナーのように考えるのか?
スタートアップの際、なぜデザイナーのように考えなければいけないのか?と思っている人もいますよね。
あくまで私見ですが、スタートアップをデザインすることは必要不可欠だからです。
それはrethinkすることであり、(デザインがなければ)会社の評価はそれだけ小さくなってしまうからです。
だから話すのです。デザインは本当に重要です。
◇何故デザインなのか?
自分のビジネスが将来どうなるかなんで誰にもわかりません。スタートアップも、何がどうなるかはわかりません。
最善策の代わりとして、『試してみる』ことができます。
あなたはマーケットにフィットする箇所を、スタートアップの中から見つけようとします。ファウンダは、開始してみるまでそのサービスがどこに向かって進んでいるのかは分からないものなのです。
たくさんの曖昧さがあります。たくさんの知らないことがあります。デザインが素晴らしいのは、それが曖昧さを許容する為の非常に偉大なプロセスであるからです。プロセスがあれば、どこに向かっているのかわかります。
1. Start with people - 人から始める
最初のステップは『人から始める』。ブレインストーミングやイケそうなアイデアの実現方法に時間を費やす代わりに、そうするのです。ブレインストーミングから始めてしまうことには本当に問題があります。外の世界に触れないままで明確化できる、という人はそう多くないのです。
では、本当の課題はどこにあるのでしょうか? 課題は生身の人間のところにあります。日々、あなたの周りの人達は問題を抱えています。あなたは助ける必要があります。
※ここでSquare創業者が引き合いに出される。彼は、人を良く観察し、カードでの買い物には沢山のプロセスが介在していることに気づいた。そして、そのプロセスって本当に必要なのか? となった。
 |
人から始めるにあたって、次の三つの質問を自分に問いかけましょう。
・人々が抱える日々の本当の課題をどのように観察できていますか?
・あなたのプロダクトを(多少手間があったとしても)ユーザが使おうとするモチベーションは何ですか?
・あなたのプロダクトの中でstep1. step2. …のような(こまごまとした)操作をユーザにさせているものは何?
2. Stop talking, start making - 話すより作る
スタートアップのアイデアは聞きたくありません。私は見たいのです。ポストイットでも構いません。できあがった何かが見たいのです。
それがあれば、皆とより早いタイミングで、より実りのある話ができるのです。
もう1つポイントがあります。よいアイデアというのは思いを巡らせているときには出てこないということです。考えることは素晴らしいことですし、よいアイデアを持っているというのもわかります。
しかし、実際にアイデアを掴む為には、作らないといけないのです。
分かりますか? 作り、試行する、ということを始めなければいけないのです。
さて、私が大好きな、作ることの力やどうやって全く作り変えてしまうかに関するIDEOでの話をします。
※鼻の美容整形に使用する器具の製作事例を紹介
 |
もう作り始めることができますね。
・プロトタイプから何を学ぼうとしていますか?
・学びたいことを迅速かつ多量に得る為に、どうすればよいですか?
・チームは、明日からでも大まかなプロトタイプを手早く作ってみせることができます
3. Prepare to throw away a lot of work - たくさんの仕事を捨てる為の心構えをする
頭にあるものを実体に落とし込むため、手早くプロトタイプを作ります。つまり、沢山の物ができあがるということです。
これでもかというくらいの山を見たこともあります。
あなたは思考を重ね、沢山のアイデアを目に見える形にします。沢山の物を作り、そして、いつかは放ってしまう必要があります。
さて、よりよくするために沢山の成果物を捨てて見せたインスタグラムという企業の話をしましょう。
彼らが最初に始めたのはBurbnというサービスでした。150人向けのベータテストを行ない、ファウンダはユーザの行動を観察しました。
なんと、ユーザは写真をアップロードしようとしていたのです。Burbnに写真のアップロードする機能はなかったにも関わらず、です。
ユーザは写真を他のサーバにアップロードし、そのURLを貼り付けることで写真をやり取りしたのです。なんでこんなイカれたことをやっているのでしょうか?
ユーザは超カッコいい写真をシェアしたかったのです。
ここで彼らは気がついたのです。「写真をシェアするというのはこんなに面倒なのか。たかが写真のアップロードをする為だけに、Burbn外のサービスで幾手間もかけないといけないなんて…」
彼らは考えたのです。「なんで、何を差し置いても(写真をシェアする機能を)提供していなかったのか? みんながカッコいい写真をシェアしたいなら、それが彼らのニーズじゃないか?」
そして彼らは6週間でインスタグラムを作りました。6週間ですよ!
なんでこんな短期間でできたかというと …Burbnのインフラストラクチャがあったからです。Burbnは非常に複雑なアプリケーションでした。だからBurbnをリビルドするのではなく、Burbnから使えそうなものを取り出して作りあげたのです。
Burbnは非常に複雑でしたが、全て捨てました。最良の部分だけを取り出し、この絞り込まれたシンプルなプロダクト(インスタグラム)ができたのです。
たくさんの人に親しまれている、それがインスタグラムです。
なので、できあがったものを捨ててしまう心構えはしておきましょう。
ここで、3つの質問があります。
・あなたは作ったものを捨てられますか?
・捨てるときに直面する困難とは?
→それが他の部分と結合してしまっているときです。
・ユーザエクスペリエンスをシンプルにする為に切り捨てられる余計な機能はなんですか?
4. Spend as much time as possible talking to people who don't start startups - スタートアップをしていない人と時間が許す限り話す
時間はできるだけスタートアップをやってない人達と話す為に使いましょう。
我々にとって、こういう場所(このイベント)に来て会話をしたり、どこかのスタートアップにいっては友達と話をしたり、スタートアップの輪とつるむのは容易いことです。なので、サンフランシスコには20代の企業家がデザインしたアプリケーションが氾濫することとなります。私だったらもっとよくすることができる、というものばかりです。
ある企業の話をしたいと思います。シリコンバレーでは無いものとされていた人達にフォーカスし、世界のどのスタートアップからも差別化した企業です。すぐに注目され、急成長したシリコンバレーのスタートアップです。
Pinterestです。Pinterestというのは仮想のピンボードです。気に入ったものをピンして、シェアすることができます。ユーザーは気に入った画像をピンできます。
デザインは綺麗かつ非常にスマートな作りで、パワフルなプロダクトです。ただ、疑問があります「これが誰かを引き付けるのでしょうか?」
ヒントはサンフランシスコにいる男性ではないということです。 …母親です。
Pinterest はたくさんの母親を引き付けているのです。500万人の母親に愛されています。ここには典型的なサンフランシスコのギークはいません。
Pinterestは女性駆動です。西海岸でも東海岸でもなく、アメリカ中部から中西部に住んでいる女性です。
彼女達はレシピをピンします。夕飯を何にするか考えたいのです。手芸のアイデアもピンします。休暇など、子供達に着せる服用のものです。
あとはかわいい子猫の写真をピンしています^^。
このPinterestの基本的な点こそが、Pinterestを怪物たらしめているのです。
Pinterestのユーザ層はいわゆるシリコンバレーのそれとは違います。
彼女達はTechCrunchを知りません。(逆説的になりますが)だから、
Pinterest はシリコンバレーの外で見出されたのです。
ではどうやって手付かずの巨大なユーザ市場を見つけるのでしょうか?
彼らには男性以外をターゲットにするということと、デモグラを使うことへの才能がありました。
だから、信じられないくらいの巨大な市場を見つけることができたのです。
あなたに必要なのは次のものです。
・スタートアップの外の世界で、誰と話していますか?
・自分が推測していることに取り組んでいますか?
・インスピレーションの為に、文化や流行あるいはそれに近い体験をどのくらいしていますか?
・あなたの市場に対し、デザインをすることができますか?
アプリケーションを次から次へと作る際、デザインは信じられないくらいの競争優位になります。友人とコラボレーションし、始めましょう。
5. Humanize your story - 自身の物語を人間味のあるものにする
最後のステップは、あなたの物語を人間味のあるものにするということです。
作業を終え、スケッチを終え、ピザをこれでもかと食べ終える頃、ユーザーの全ての困難と向き合いたいという欲求がでてきます。
言いたいのは、彼らはそんな困難を求めていないということです。
広告なのですが、このビデオを見てください。
これはカナダのイヌヴィク(Inuvik)という小さな町のビデオです。この町では1年のうち1ヵ月、日が昇らないのです。
トロピカーナは10万ルーメンの明かりでこの小さな町を照らしました。
人はあなたが作ったものから、何かを経験します。
人はあなたがこの世界へもたらしたものに興味を惹かれます。
人は特徴を友人やチームへ話そうとします。
人は製品に隠れた力を、余すことなく友人へ話そうとします。
何を感じたかを覚えているのです。だからあなたの作ったものを愛するのです。
人を射抜く為に最初にできて最高の方法は、人に調和し寄り添うことです。
なぜならデザインは人々を射抜き、人々に入りこんでいくものだからです。
どうやってユーザを通じ自分の物語を人間味のあるものにするかについての素晴らしいビデオを見せたいと思います。
Tropicana - Soleil
ありがとう。
----
以上です。
Elle Luna様、Brenden Mulligan様、Open Network Lab様、お疲れ様でした。
登録:
投稿 (Atom)